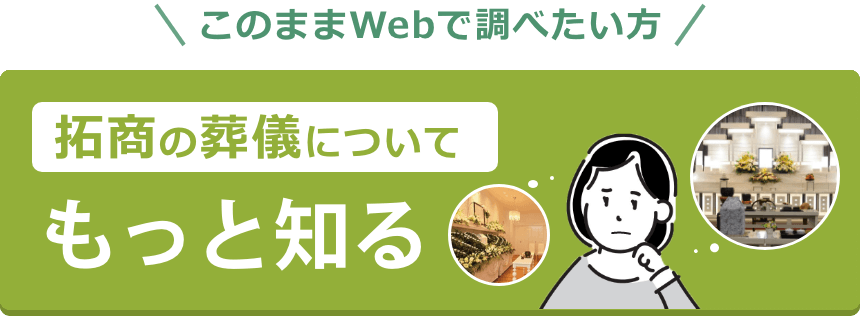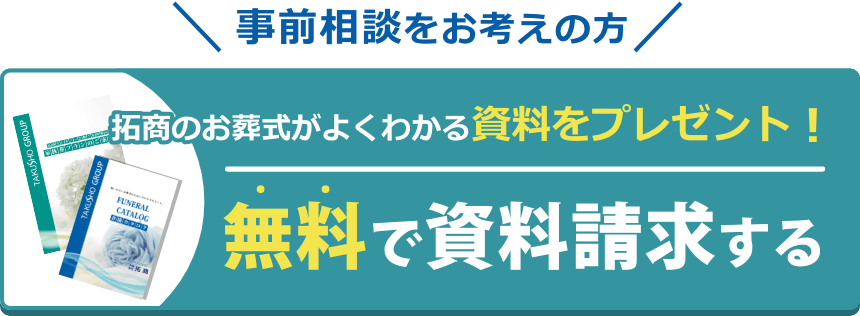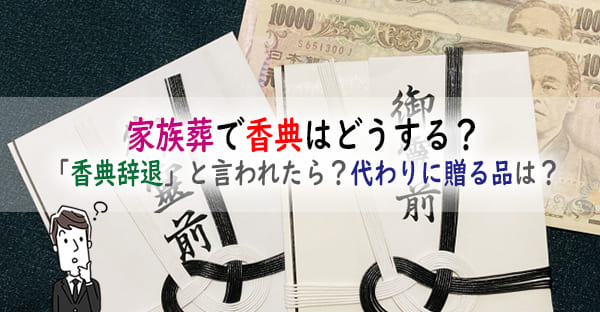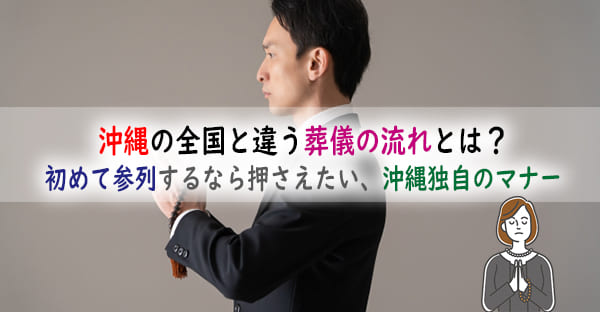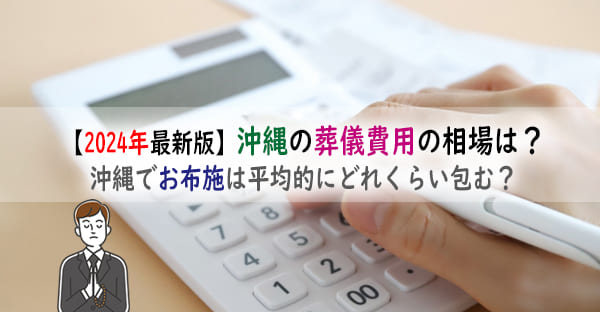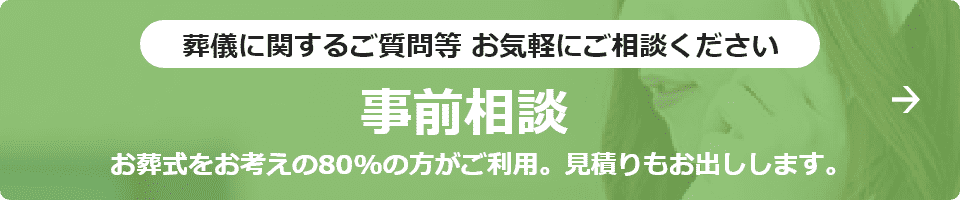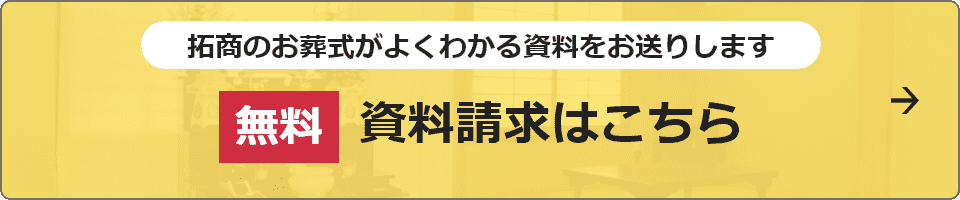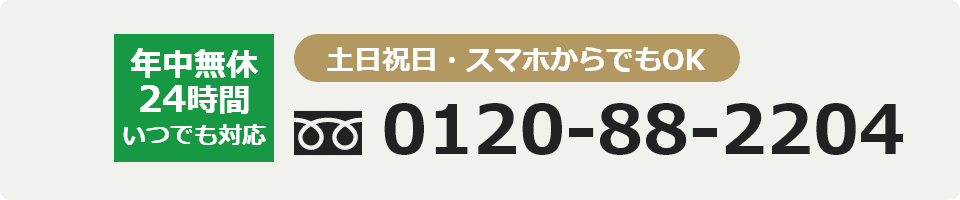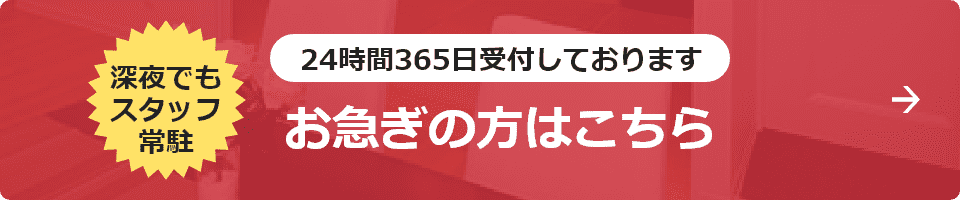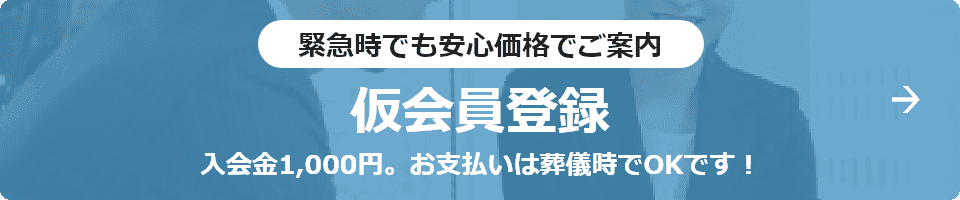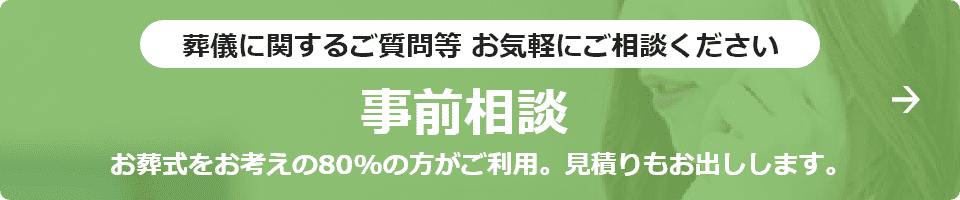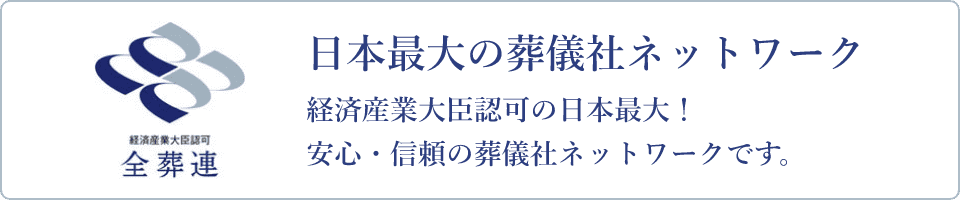お葬儀の豆知識
沖縄の葬儀や納骨式は本州と何が違う?初めてなら押さえたい、沖縄の葬儀5つの特徴とは
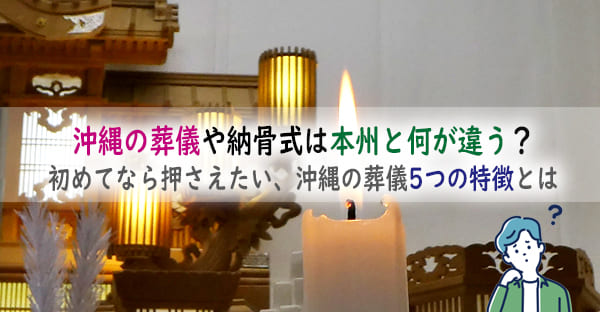
・沖縄の葬儀は、本州と違いはある?
・沖縄の葬儀で押さえるべき違いとは?
・沖縄の葬儀はなぜ、本州と違いがあるの?
「琉球王朝」と言う、本州とは違う独自の歴史文化を持つ沖縄では、葬儀も本州とは違いがあります。
そのため初めて沖縄の葬儀に初めて参列する時には、その違いを理解し、沖縄の葬儀ならではのマナーを押さえることが大切です。
本記事では、沖縄と本州の葬儀の違いが分かり、初めて沖縄の葬儀に参列する際にも失礼にならない、沖縄ならではの葬儀の特徴が分かります。
沖縄の葬儀:通夜の違い

◇沖縄の通夜は僧侶を呼びません
現代、本州では通夜と葬儀の両日を通して僧侶をお呼びし、参列者を受け入れて読経供養を執り行いますよね。
そのため友人知人であっても、通夜と葬儀の両日訪れる参列者は多いです。
一方沖縄の通夜は、ごく近しい家族や親族のみで執り行い、参列者を受け入れず、僧侶もお呼びしません。
沖縄の通夜は「ユートゥージ(夜通し)」などと呼ばれます。
今はすっかり見なくなりましたが、昔ながらの沖縄の通夜では、家族やごく近しい人々がお線香の火を絶やさずに、故人の傍で見守り、故人を偲ぶ時間です。
沖縄には「檀家制度」がない
◇沖縄には「檀家制度」「菩提寺」の風習がありません
沖縄の通夜で僧侶をお呼びせず、ごく近しい家族や身内で見守るのは、そもそも沖縄に「檀家制度」がないためです。
菩提寺と檀家は代々家で深い関係性にあり、檀家の家族が亡くなると、通夜や葬儀など全ての儀式を菩提寺が担い、檀家は寺院を経済面などで支える制度です。
本州では江戸時代に檀家制度が戸籍と同じ役割を果たしたため、檀家制度が根付いてきましたが、沖縄は独自の琉球王朝の歴史や文化があるため、檀家制度が根付いていません。
沖縄で僧侶の手配はどうする?
◇沖縄では葬儀社などに相談し、手配しましょう
檀家制度が根付く本州では家族が亡くなるとまず、菩提寺に相談をします。
菩提寺に相談をしないまま葬儀を済ませたり、ネットなどで戒名を付けたりすると、お墓に納骨できないトラブルも起こり得るためです。
けれども沖縄にはそもそも檀家制度が根付いていないため、僧侶の手配は自由です。
・近隣の寺院のご住職に相談する
・葬儀社に相談する
・仏壇仏具店、霊園などに相談する
個人墓地が多い沖縄では、民間霊園は増えてきたものの、寺院墓地は少ないですから、基本的には葬儀社や仏壇仏具店など、専門業者に相談し手配します。
ただ特定の宗旨宗派にこだわらない家が多いため、本州で増える無宗教葬と同じく、実は必ずしも読経供養を必要としません。
沖縄の葬儀:火葬の違い

◇沖縄では葬儀の前に火葬を済ませます
全国的には葬儀の後、身内のみで火葬場へ向かい火葬を済ませますよね。
葬儀の後、斎場の玄関先で参列者に見送られ、ご遺体は身内とともに火葬場に向かいます。
葬儀当日の午前中に身内のみで火葬を済ませ、ご遺骨の状態で葬儀を執り行います。
そのため沖縄の葬儀は一般的に午後から執り行うものが多く、参列者は斎場前でご遺体のお見送りがありません。
沖縄では葬儀当日に火葬をする
◇沖縄では葬儀当日、葬儀前の火葬を行います
沖縄で火葬は葬儀当日の午前中に行う流れが多いです。
葬儀後に斎場前で行う喪主挨拶や、参列者によるご遺体のお見送りはありませんが、ご遺族は葬儀前に「お別れの時間」を設けます。
家族や近しい親族はもちろん、生前に故人と親しい関係性にあった友人などが、火葬前の故人とお別れをすることもあるでしょう。
沖縄の葬儀自体は規模が大きく参列者も多いため、葬儀前に身内でお別れ会・火葬を済ませる流れも頷けます。
沖縄の葬儀:参列者の違い

◇従来の沖縄の葬儀では、規模の大きなものが多いです
昔ながらの沖縄の葬儀は、一般の人々でも参列者が100人を超えるような、規模の大きな葬儀が少なくありません。
そのため沖縄の葬儀会場は一般的に、祭壇から前半分は喪主・ご遺族や親族が向かい合い座り、後ろ半分から一般参列者の席になる配置が多いでしょう。
沖縄の葬儀会場における席順について、下記コラムではイラストにて詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
・【葬儀の進め方】トラブルの多い葬儀での席順。喪主が配慮する5つの事柄
沖縄のお悔やみ欄
◇沖縄の葬儀は、新聞の「お悔やみ欄」に掲載されます
沖縄の葬儀は一般の人々でも新聞の「お悔やみ欄」にて、広く案内を掲載します。
沖縄の二大新聞紙「琉球新報」「沖縄タイムス」両方に葬儀案内を掲載する「荼毘広告(だびこうこく)」を依頼する流れです。
現代は「お悔やみネット」など、ネット上の案内サービスも登場しました。
沖縄の人々は訃報を受けると、翌朝のお悔やみ欄で葬儀情報を確認します。
当然沖縄では参列者を限定することなく受け入れるため、一般の人々でも葬儀の規模が100人以上を越える規模の大きなものが多いのです。
・沖縄の葬儀は新聞で案内を出す?「お悔み欄」確認の仕方や掲載の流れ、料金目安を解説!
沖縄の葬儀:納骨の違い

◇沖縄では葬儀当日の納骨式も多いです
全国的には四十九日法要の後、納骨式を行う地域が多いですよね。
四十九日法要までにお墓の彫刻などを済ませるため、準備が必要です。
全国的な先祖代々墓は納骨にあたり、故人の名前や没年月日などを彫刻しますが、沖縄の「門中墓」は、特別な準備が必要ないためです。
また沖縄ならではの風葬の歴史も影響しているでしょう。
戦後までご遺体をお墓内に置き、風葬していた沖縄では、すぐにご遺体をお墓に納める必要がありました。
沖縄のお墓「門中墓」とは
◇「門中墓」とは父方の血族によるお墓です
全国的には家族が亡くなると先祖代々墓に埋葬されますが、沖縄では父方の血族が入る「門中墓」に入ります。
その家のご先祖様が入る先祖代々墓とは違い、父方の血族で集まる門中墓は人数が多く、なかには何千単位の門中もあるほどで、故人の名前や享年月日を彫刻する風習はありません。
ただし嫡男ではないなど、新しくお墓を建てる沖縄の人もいます。
この場合には、お墓が建つまで納骨できないので、沖縄であっても葬儀当日の納骨式はできません。
沖縄の法要「なーちゃみー」とは?
◇「なーちゃみー」とは納骨式翌日のお墓参りです
昔ながらの沖縄の葬儀では、葬儀当日に納骨式が行われ、翌日にお墓参りをしてお墓の様子を確認する「なーちゃみー(翌日見)」がありました。
沖縄には風葬の歴史があるため、故人が生き返る「黄泉がえり」がないかを確認する儀式だとも言われます。
そのため現代では、なーちゃみーの儀式を行う家も、あまり見かけなくなりました。
沖縄の葬儀:香典の違い

◇沖縄の葬儀で持参する香典は、相場が低い傾向です
従来の沖縄の葬儀では、持参する香典金額相場が約千円~3千円ほどとなり、本州の葬儀とは香典相場が異なります。
けれども沖縄で葬儀に参列すると、知人友人の香典相場は約千円~3千円となります。
住民同士がお互いに負担にならぬよう、地域によっては住民の参列において「一律千円」と、自治体で定められていることもあるでしょう。
前述したように規模の大きな葬儀も多い沖縄では、香典相場が低い一方で、会葬御礼のみで香典返しを送らない葬儀が多いです。
香典袋のマナー
◇香典金額が5千円以下であれば、水引が印刷された香典袋を選びます
本州の葬儀は一般参列者であっても、香典金額が約5千円以上のものがほとんどです。
香典袋は白と黒の水引がついているものが多いでしょう。
香典袋は金額に比例して選ぶためです。
千円~5千円未満の場合、香典袋は水引が印刷されたものを選び、5千円以上であれば水引が付いたものを選びます。
まとめ:沖縄と本州の葬儀の違いは、規模の大きさです

荼毘広告を手配して新聞のお悔やみ欄(訃報欄)に葬儀のご案内が掲載される沖縄では、多くの人々が葬儀に参列し、お焼香に長蛇の列を作ります。
そのためご遺族は葬儀前に火葬を済ませ、遺骨の状態で葬儀を始める他、基本的には葬儀後のお斎(会食)の場なども設けません。
参列者は列に並びお焼香を済ませると、すぐに帰る人が多いためです。
ただ近年では沖縄も家族葬など、参列者を限定した規模の小さな葬儀が増えています。
規模の小さな葬儀では、本州の習慣と同じく、参列者へ御案内状を送り、執り行う流れが一般的です。